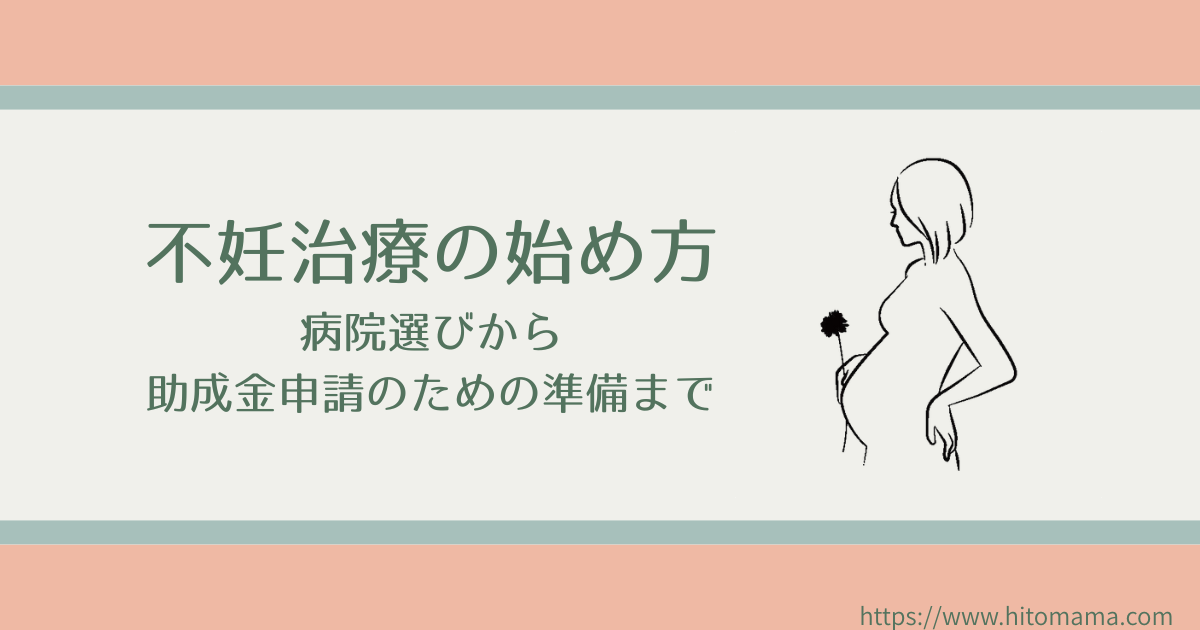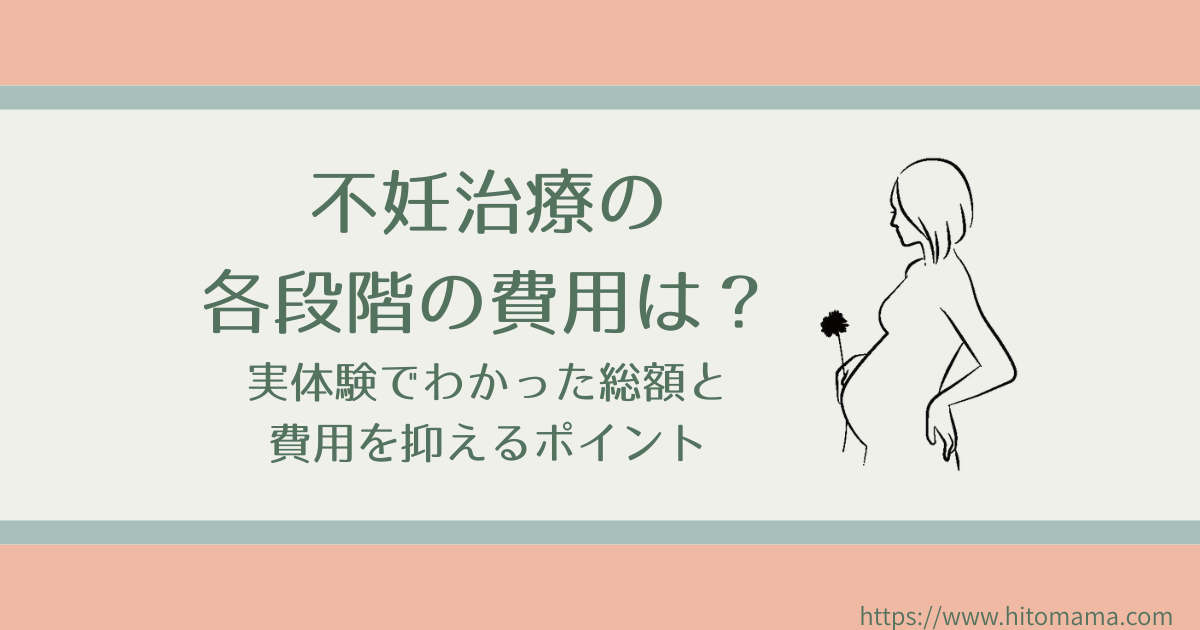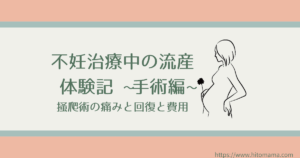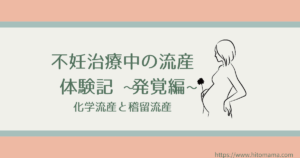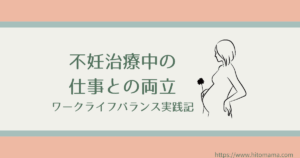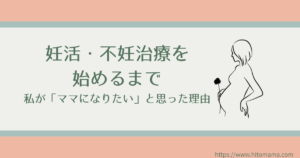こんにちは、風香りんです。
今回は、私が不妊治療専門クリニックを選んだ理由や、実際の通院の流れ、治療のスケジュールについてお話しします。さらに、助成金や医療費控除を受けるために、治療の初期から気をつけておくべきことについてもまとめてみました。
不妊治療は、体や心、時間、そして費用など、さまざまな面で負担が大きいものです。この記事が、これから不妊治療を検討している方の不安を少しでも和らげ、一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。
病院選びのポイントと、私がこのクリニックを選んだ理由
不妊治療は、仕事やプライベートのスケジュールとは別軸で、体調や生理周期に合わせて何度も通院する必要があるため、病院選びは非常に重要です。私がクリニックを選ぶ際に重視したのは、以下の3つのポイントでした。
職場からの通いやすさ
不妊治療は、仕事の重要な日であろうと、体のリズムに合わせて通院しなければならない場合があります。そのため、私は勤め先から徒歩8分のクリニックを選びました。
朝、診察を受けてから出社してもギリギリ間に合いましたし、退勤後も少し早退するだけで通院できたので、仕事との両立がしやすかったのが大きなメリットでした。
仕事との両立を謳っているか
ホームページで「仕事との両立」を謳っていたことも、このクリニックを選んだ理由の一つです。
ただ、実際に通い始めてから、診察受付の時間が早い項目もあると知って少し戸惑うこともありましたので注意が必要です。細かく知りたいかたは事前に電話などで聞いてみるといいと思います。私が通っていた病院は、ホームページのどこにも、どの項目だと何時まで、というような案内はありませんでした。
が、多くの患者さんが仕事と両立しながら通院している環境だったので、安心して通うことができました。
知り合いに経験者がいた
実は、私の会社の先輩がこのクリニックで不妊治療を経験していました。実際に身近な人が妊娠したという話を聞けたことは、病院を選ぶ上で大きな安心材料になりました。
このブログが、読者のあなたにとって、そんな身近な存在になれたら嬉しいなと思っています。
ちなみにその人は、その妊娠でしっかり出産までたどり着くことができ、私の1年半先輩ママとして、現在も子育ての様々なことでアドバイスをもらったり、育児グッズをお借りしたりしています。
通院開始!初診と検査の流れ
初診は電話で予約し、事前に簡単な問診票をインターネットで提出しました。
大規模な病院だったため、2回目以降は専用のアプリで予約し、診察券を使った自動受付やメールでの呼び出しなど、効率的なシステムで動くことになります。慣れるまでは少し戸惑いましたが、スムーズに診察が進むのは助かりました。
最初の周期は検査ばかり
不妊治療の最初の周期は、検査ばかりで治療に進みにくいのが一般的です。これは、この時期に行う検査には自費診療が多く、治療と検査を同じ周期に行うと「混合診療」となり、せっかく保険が適用される部分もすべて自費になってしまうからです。
私が受けた初期の検査は多岐にわたり、覚えているだけでも以下のようなものがありました。
- 血液検査
- 子宮の形の検査(生理期間は不可)
- 卵管が詰まっていないかの検査(生理期間は不可)
検査によっては生理期間中に行えないものもあるので、初診の予約は生理直前ではなく、生理が終わってすぐのタイミングに合わせると、効率的に進められるかもしれません。
不妊治療の流れと「ステップアップ」
ここからは、私が実際に経験した不妊治療の流れと、それぞれの段階での通院回数についてお話しします。
この3ステップがベースにはなりますが、他にも流産手術や凍結胚の保管などの費用はかかります。費用の全体間についてはこちらの記事をご覧ください。
タイミング法
排卵日を予測して性交渉のタイミングをアドバイスしてもらう方法です。卵胞の成長具合を見るために、排卵日近くに2~3回通院しました。
年齢にもよりますが、通常は数回チャレンジします。私は20代でしたが、2回で次のステップに進むことを決めました。 タイミング法の詳細はこちらの記事で解説しています。
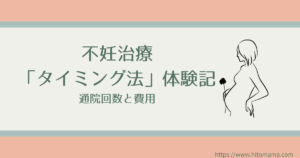
人工授精
病院で処理した精子を、排卵直前に医療器具を使って直接子宮内に注入する方法です。通院回数はタイミング法とほぼ同じでした。
タイミング法と比べて劇的に妊娠確率が上がるわけではないと聞いていましたが、私は3回でステップアップしました。 人工授精の詳細はこちらの記事で解説しています。
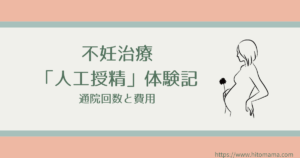
体外受精
採卵周期と移植周期に分かれます。私の場合は、卵巣への負担を考慮して、それぞれ別の周期で行いました。
- 採卵周期: タイミング法や人工授精と同じように、排卵日近くに何度も通院し、卵を育てるための注射も打ちます。そして、採卵手術の日に通院します。
- 移植周期: 生理開始後、排卵直前、移植日、そして妊娠判定日の4回が基本的な通院パターンでした。
詳しくは別の記事で紹介しますが、私は採卵を2回、移植を4回経験しました。体外受精はさらに費用がかさむため、自治体からの助成金や医療費控除、高額療養費制度などを賢く活用することが大切です。 体外受精の詳細は採卵編と移植編の2記事で紹介しています。
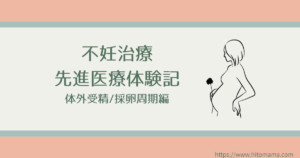
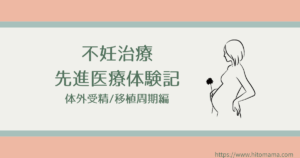
医療費控除を受けるために絶対やっておくべきこと
不妊治療を始めると、保険適用であっても医療費が跳ね上がります。そこで活用したいのが「医療費控除」です。
医療費控除は「その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費総額」が対象になります。不妊治療の費用だけでなく、他の医療費もすべて合算できるので、窓口で支払ったすべての領収書を必ず保管しておきましょう!
保険組合によっては、10月頃に送られてくる「医療費のお知らせ」を活用する手もありますが、念のため自分で領収書を管理しておくと安心です。
医療費控除の手続きをした時の話は今後別の記事を作って解説する予定です。
まとめ
不妊治療を始める前の私は、何から手をつけて良いかわからず、とても不安でした。しかし、通いやすいクリニックを選び、一つずつ検査や治療を進めていく中で、少しずつ前向きな気持ちになれたのを覚えています。
まずは、あなたにとって最適なクリニックを探すことから始めてみてください。そして、医療費控除のために、領収書だけは忘れずに保管するようにしてくださいね。
他にも、不妊治療に関する体験記をお届けしますので、楽しみにしていてください。